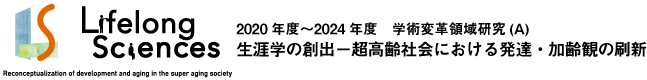Interview 07:
ヒトモノ班代表
倉田誠(くらた・まこと)
既存の生涯観の革新を目指す生涯学において、なぜ「ヒトとモノの関係」をテーマにした文化人類学の班が作られたのか。サモアで長く“障害”に関するフィールドワークをしてきたヒトモノ班の倉田さんに伺いました。
<記事公開日> 2022.9.28
ご専門の「医療人類学」とはどのような研究分野ですか?
簡単に言うと、病気に関する人びとの考え方や医療に関連するさまざまな現象を対象にする文化人類学の一分野です。私の主なフィールドはオセアニアのサモアで、人々がいわゆる“障害”をどう受け止め、どう対処しているかをフィールドワークによって調査しています。
障害の受け止め方は日本とはだいぶ異なるのでしょうか?
私がフィールドに入った当時は、「健常」と「障害」という区別がなかったですね。そもそも、「人はこれぐらいできるのが“普通”」という考え方をしていないのです。
サモアでは家族の中で子どもも、子守や家事をします。上の子が弟妹に仕事をさせるときには、「この仕事はこいつにはできないから、別の弟にやらせよう」とか、「妹はこの仕事をやらないから、あっちの仕事をさせよう」という形でやりくりしています。
高齢で足が不自由になった人は、杖などはほとんど使わず子どもや孫の肩を借りて車まで移動しますし、自分の手が届かないところに必要なものがあれば、やはり子どもを呼んで取ってもらっています。
ほかの人と同じようにできないならできるように訓練しよう、車椅子などを使って本人の不自由さを低減しよう、と考える日本や欧米のやり方とはちょっと対照的ですね。
実はサモアでも、十数年前から現地のNGOにオーストラリアなどからの援助が入って、車椅子や起立支援のリハビリ用具が提供され始めました。
しかし、そうした“モノ”をもらった人は、周囲から「特別な支援を必要とする人」と見なされるようになっていきました。それまで区別されていなかったのに、人がモノと組み合わさったことで「特別なニーズを持った者」とみなされるようになったのです。サモア語には存在していなかった「障害(Disability)」という言葉の訳として、「スペシャル・ニーズ」を意味するサモア語(Manaoga fa’apitoa)があてられるようになりました。

人間を評価するときに、生身の本人だけでなく“モノ”が関わっている。それが、私がヒトとモノの関係に注目したきっかけでした。
そのようなところに生涯学の準備段階でお誘いをいただき、喜んで「ヒトモノ班」として参加させていただきました。
私たちの班には、さまざまなヒト・モノ関係を研究する専門家が集まっています。自助具、義足や義肢、生理用品、楽器、育児具や介護具、フィットネス用具などなど……。文化人類学者だけでなく、発達心理学者や福祉工学者、理学療法士の方もいます。また、障害だけでなくジェンダーという視点からヒトとモノとの関係を考えようとしている方もいます。
コロナ禍で海外調査ができなかったぶん、国内でフィールドを共有しながら共同調査を行い、畑違いの研究者の鋭い視点や新鮮な疑問に刺激を受けながら研究を進めているところです。
異文化を観察してきた文化人類学者から見て「人間は、生まれて、成長し、やがては衰えて死ぬ」という生涯観は、日本に限らず普遍的なものだと思いますか?
フィールドワークでずっと個々の事例を見てきた私としては、サモアだろうが日本だろうが「“標準的な”成長から衰退までを描く曲線」に沿った人生を歩む人のほうが少数派ではないかと思っています。
これという障害や病気がなく、20~50代であれば「自分は障害や加齢による不自由さとは無縁の、自立した存在だ」という感覚を抱きがちですが、それは幻想に近い。実際には誰もが、モノやサービスに支えられた上で能力が発揮できているのですから。
標準的な曲線からすると、40代の私はまだ本格的な衰えより前にいることになっています。しかし私の視力は10代で大きく低下しました。もしメガネという“モノ”がなかったら私はフィールドワーカーにはなれていなかったかもしれません。
サモアで調査をしていると、私が当然のように依存しているメガネやサンダルなどの“モノ”がないと、私自身は、周りの人が当たり前にできていることを「できない」人間であることに気づかされる場面がたびたびあります。
つまり、生身の人間の能力というより、モノとヒトが組み合わさって生みだされるものにもとづきながら私たちは生きています。同じ人物に対しても、モノとの関係によって評価が変わりうるわけですから、「標準的な成長―衰退」というモデルが通用する場面、当てはまる人はごく限られていると思います。
それに変わる新たな生涯観の提示が生涯学における文化人類学の役割でしょうか?

新たな生涯観を提示するというより、日本でふつうに思い描く“典型”から外れている人々の生き方を拾い上げていくことで「人の生涯はこうであるはずだ、こうであるべきだ」という概念的な縛りを解き、新たな生涯観を模索するための視点を提供できればと思っています。
日本の小学校の音楽の授業では全員がリコーダーを吹くことになっていますが、指や腕が不自由な人にとって、リコーダーはとても難易度の高い楽器です。
そのとき、「自分の体でも吹けるようにリコーダーに手を加える」という方法もあれば、「通常の奏法や姿勢とは違う方法で吹く」方法もありえる。「リコーダーではなくピアニカで演奏する」という選択肢もあるはずです。
ただ、日本では“標準”に寄せようとする圧力が非常に強い。昔の話ですが、片手が不自由な生徒が自分なりにリコーダーを加工し、オリジナルの運指で吹けるようになっても、試験で運指を問われ、標準の運指とは異なる回答だったためにバツをつけられたという話も耳にしました。
そのような社会では、標準的に物事をこなせなくなったら「もうダメではないか」と不安になります。それでは、加齢や障害によって人は苦しくなるばかりです。
一方、サモアでは、「Aができないなら、Bで代替すればいい。CさんができないことはDさんにやってもらえばいい」というように、ダメだったときに別の選択肢が多いように感じます。もしかしたらそういう社会のほうが、高齢になっても、障害を持つことになっても生きやすいかもしれません。生涯学で私たちの班は、そうした社会を成り立たせる基盤を探っていきたいと考えています。
リコーダーを例にとるなら、教育学と連携することで探ることができるかもしれません。あるいは奏法の工夫に着目すれば、文化人類学の技能班の方々との議論も可能でしょう。他分野、他領域の方々と「これがダメならあれで」という生き方を支える社会の実現に必要なものを考えていけたらと思っています。
<プロフィール>
倉田誠(くらた・まこと) 東京医科大学医学科・准教授
三重県生まれ。神戸大学や国立民族博物館などでの研究員を経て、2014年より東京医科大学へ。2020年から現職。専門は医療人類学、生命倫理学、障害学、オセアニア地域研究。長期にわたるフィールドワークを通じて、サモアにおける病気や障害のとらえ方とその変遷を記述してきた。共著に『交錯と共生の人類学――オセアニアにおけるマイノリティと主流社会』(ナカニシヤ出版)など多数。

<取材日>
取材日 2022.8.31
取材・構成:江口絵理
撮影:植田真紗美