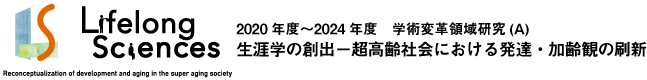アフリカの野生チンパンジーを研究している松本卓也さんが、生涯学プロジェクトの公募研究に参加されました。類人猿のフィールドワークは生涯学にどのような示唆をもたらすか――。実験心理学を専門とする知覚・認知心理班の寺本渉さんが伺います。
<記事公開日> 2024.6.17
チンパンジーとヒトの「高齢者の生きざま」を比較
寺本渉(熊本大学大学院人文社会科学研究部)× 松本卓也(信州大学理学部)
野生チンパンジーで「おばあちゃん仮説」を検証してみよう
寺本:生涯学の研究はこれまで、ほぼすべてがヒトを対象としたものでした。チンパンジーの研究者である松本先生が加わられたことによって、種を超えて、つまり「生物」として加齢をとらえなおせるのではないかと非常に期待しています。
松本:ありがとうございます。チンパンジーは遺伝的にヒトに最も近い種ですし、寿命もそれなりに長いので、生涯学における種間比較の対象として興味深い存在だと思います。
寺本:チンパンジーの寿命はどれぐらいですか?
松本:ヒトと同様、一口に何歳とは言えませんが、野生では50代が最高齢と言えそうです。
寺本:となると、何歳以上が高齢チンパンジーとされるのですか?
松本:いろんな定義がありえますが、私の研究では、生物学的な年齢や見た目で区切って“高齢”な個体を対象にするのではなく、「娘と孫をもつメス」に注目しようと考えています。
チンパンジーは雌雄が複数集まって集団を形成し、集団のなかでは乱婚です。メスは生殖可能な年齢に近づくと別の集団に移籍し、出自集団とは完全に縁が切れます。ですから、基本的にメスは自分の娘の子、つまり孫に会うことはありません。
ところが観察を続けるうちに、私は、出自集団から出て行かないメスが一定の割合でいることに気づきました。さらに、そうしたメスが出産して「祖母と孫」という関係が生まれ、祖母が孫の世話をする様子も確認しています。
そこから、閉経後のメスの長寿について、「自分の子を残すという点では閉経後のメスが長生きすることには意味がないように見えるが、自分の子や孫を助けることで自分の遺伝子をより多く残すことに貢献している」と説明する「祖母仮説」の検証ができるのでは、と思い立ち、生涯学の公募研究に応募しました。

また、チンパンジーのオスは、乱婚社会ゆえに誰が自分の子や孫かわからないとされていますが、もしかしたら実際はわかっていて、狩りに成功したときに優先して肉をわけてあげたり、ふだんの生活で優先的に遊んであげたりしているかもしれません。
「高齢」とまでは言えないかもしれませんが子をもてる程度に年長になったオスが、その後、加齢によってただ体が衰えていくだけでなく、なんらかの役割をになっているかどうかを見てみたいと思っています。
寺本:加齢の兆候ははっきりわかるんですか?
松本:老眼なのか、毛づくろいのときに手元からぐっと目を離すような仕草をしたり、体毛に白い毛が増えたり、という変化はあります。ただ、メスに閉経があるかどうかはわかっていません。
行動観察、人口動態データ、DNA分析の合わせ技で挑む
寺本:いわゆる“高齢”チンパンジーの役割を、どうやってたしかめるのですか? 私は実験心理学が専門で、さまざまな条件を整え、つまり「操作を加えて」ヒトの行動や反応を観察する分野なので、野生チンパンジーを対象にした研究がどのように進められるのか、興味があります。
松本:たしかに、私の研究は寺本先生と対照的に「できるだけ操作をくわえずに」ありのままを観察する研究です。どちらかというと文化人類学の研究に近いですね。
私の調査地は東アフリカのタンザニアで、野生チンパンジーの野外調査がおよそ60年続いてきたマハレという場所です。そこで暮らすチンパンジーたちの個体識別をして、ひたすら森の中で彼/彼女らにくっついて歩き、行動を観察・記録します。操作は一切しないので、たとえば、祖母仮説の検証をしたいというテーマをもっていたとしても、それを検証できるような行動が観察できるとは限りません。
ただ、すでに祖母-娘-孫関係が確認できているメスたちがいるので、彼女たちの生活をつぶさに観察することが本研究における中心的な調査となります。
寺本:オスの役割はどう調べるのですか? チンパンジーは、母子は常に密着しているから親子関係は明らかですが、父子関係は人にはわかりませんよね?
松本:採取した糞のDNAから調べます。観察対象の集団のオスと子どもたちの父子関係を調べておき、肉の分配や遊んであげる行動を観察して、あるオスが特定の子を優遇しているかどうかを記録して血縁の有無とすりあわせる、という形です。
また、公募研究の2年間の行動観察だけでは量的な考察は不可能ですが、マハレにはチンパンジーの人口動態データが数十年にわたって蓄積されています。データをもとに、“高齢”のオスやメスが、自身の繁殖行動以外に子孫を残すことにどれだけ貢献しているかを探れればと思っています。
寺本:いまのところ、祖母仮説や、高齢オスの役割は「ありそう」なのでしょうか?
松本:まったくわかりません。祖母仮説は生物学的に非常に魅力的な仮説ですが、どの動物でも検証は非常に難しい。けれどチンパンジーで祖母ー孫関係が観察できるなら検証できる可能性がある。だからトライしてみよう、という段階です。
「サクセスフル・エイジング」への示唆になるか?
寺本:いま「サクセスフル・エイジング」に注目が集まっています。生涯学プロジェクトでも、ヒトは生物学的には衰えていくけれど、それだけが加齢ではなく、加齢のポジティブな側面にも目を向け、加齢をとらえなおそう、という方向性を打ち出しています。そうした観点からすると、松本先生の研究はどのような示唆をもたらすと期待できるでしょうか?
松本:生涯学では、「ヒトは生まれ、成長し、ピークを迎えたあとは衰えていく」という一面的な生涯観を相対化しようとしているのだと理解しています。チンパンジーで高齢個体の社会的な役割がわかると、高齢チンパンジーもただ生物学的に衰えていくだけの存在でなく、「社会と関わり、高齢ならではの他者との関係性をつくっていく存在」と考えられ、旧来の生涯観をとらえ直すきっかけを提供できると思います。
寺本:仮に「チンパンジーでも祖母仮説が成り立つ」「高齢個体にはこのような役割があった」となったら、「ヒトの高齢女性もそうした役割を果たしながら生きることがサクセスフル・エイジングにつながる」と言えますか?
松本:いえ、「チンパンジーが、あるいは自然界がこうなっている」ということがわかったとしても、「だから人間もそのようにあるべきだ(それが幸せだ)」という話に持っていくことはできないですね。
私が明らかにしようとしている“役割”とはあくまで生物学的に「その個体が自分の子孫を残すことにどれだけ寄与したか」という観点で見たものです。
高齢になっても生物学的な役割があるという事実がわかったから、高齢者も社会に存在する価値がある、というように、「事実(=である)」を「価値(=べき)」の話に変形するのは論理的に無理がありますし、そうした価値付けは容易に反転して「役割を果たしていない人は価値がない」という話になってしまいます。
祖母仮説や高齢オスの役割の検証は、人間の高齢者の価値や存在意義を肯定したり否定したりするための研究ではなく、あくまで生物学的な関心から始めたものです。
寺本:なるほど。では、この研究で「種間比較」をしたい、というのはどういう意図ですか?
松本:生涯学で刷新しようとしている生涯観は、現代日本の生涯観ですよね。ほかの地域の生涯観とすりあわせれば、現代日本の生涯観、自覚せずに「当たり前だと思いこんでいた生涯観」がゆさぶられ、それを相対化するきっかけとなる。それが文化人類学班がなさっていることだと思います。
同じことを、地域や文化の違いによる相対化ではなく、種の違いによって、ヒトという種が共通してもっている思い込みのようなものを発見するきっかけになれば、と思っています。他者のなかにどっぷり入ってみないと、自分たちの特殊性には気づきませんから。
寺本:文化人類学にはできず、類人猿研究だからできることはありますか?
松本:人間を対象とした場合、簡単にDNA分析による父子判定ができないといった理由から、「その行動があったから生き延びられた、子孫を増やせた」(=適応的に意義がある)ということを検証するのはなかなか難しいだろうと思います。いくらでも解釈の余地が生まれてしまう。一方で、チンパンジーの研究は生物学的な基盤のもとで、人口動態データやDNA分析の結果によって適応的な意義を検証しやすい、という違いがあると思います。
孫の世話は高齢チンパンジー自身に利益がある?

寺本:松本先生の過去のご研究で、チンパンジーの赤ちゃんの離乳時期に関する論文がありました。離乳の時期を乳児の目線で考えてみると外から見た時期とは異なるという報告です。乳児の目線でとらえる、という点に興味を引かれました。
そこから思いついた疑問なのですが、祖母仮説においては、子孫が享受する利益にフォーカスが当たりがちです。でも、祖母自身が利益を受けることはないでしょうか? たとえば孫の世話を通じて社会的な関係が充実するなど……。人間だと、他者との関わり、すなわち社会的な活動が高齢者の認知能力の維持によい効果があるという報告が増えています。チンパンジーでもあるでしょうか?
松本:たしかに、赤ちゃんをつれたメスたちは互いの子がじゃれあって遊ぶため、近くにいることが多くなります。それによって毛づくろいなどが増え、社会関係が広がったり密になったりしているかもしれません。ただ、最初の前提として、そもそもメス本人にとって社会活動の活性化が「よいこと」かどうかがわからないんですよね。
寺本:なるほど。ちなみに、認知症の高齢チンパンジーはいますか?
松本:わからないですね……。認知症にかかわらず、見慣れない行動や変化が観察されたときに、それを加齢や認知症によるものと断定することができないんです。単に本人の個性や、その場の状況に応じて出てきた行動かもしれないので。
寺本:白い毛が増える、などのわかりやすい見た目の変化以外に、高齢チンパンジー特有の行動の変化は見られない、と。
松本:観察例がないわけではないんですけどね。たとえば、昔、研究者がサトウキビでチンパンジーを餌付けして観察していた時期があるのですが、それを覚えていた高齢のオスが、最近、観光客の宿泊施設の外にうっかり置きっぱなしになっていたサトウキビを偶然見かけて食べたんです。そうしたら、サトウキビを食べたことのないほかの若いチンパンジーが真似をして食べ始めた、ということがありました。ただ、そのような「高齢で経験を重ねたことによる知恵」がほかの個体に影響を及ぼすような事例はそうそう観察されるものではないので、少ない事例を一般化して何かを論じることはできないんです。
寺本:そこが実験心理学との大きな違いでもありますね。私はDNAメチル化などのように、できるだけ客観的な指標で加齢や高齢をとらえる方法になじみがあるので、そのような向き合い方は新鮮です。
論文になりにくい重要な問いを議論できる場が「生涯学」
松本:実験心理学のように厳密に条件をそろえたり被験者を集めたりすることはないにせよ、私も、論文では一定の枠組みや基準を定め、それをどのように検証しうるか、データから何が言えるかを書きます。生涯学の公募研究でもそれを一つの成果として目標としています。
一方で、「その枠組みでいいのか?」「そういう基準は妥当なのか?」という問いはいつも持っていて、それは論文のなかで議論するよりも、こうした対談や領域会議での議論によって、考えを深めていけたらと思っています。
たとえば、寺本先生がさきほど投げかけてくださったような、「祖母仮説がチンパンジーで検証されたら、人間の高齢女性にも役割があると言えるか」という問いをいただいたら、「なぜ、人間の女性にばかり祖母仮説的なもの(つまり存在意義)が必要とされるのか」という問い返しができるかもしれません。
ヒトの男性も高齢になれば精子の活性や子育ての体力が下がるので、繁殖という意味では存在意義は下がる。役割だけで考えるならば、祖父仮説だって必要だという話になります。個人的には、人が生きる価値を「役割があるかないか」で決める必要はないと考えていますが。
そうした「枠組み自体を問うこと」「枠組みを応用することの問題」はなかなか論文にはなりませんが、生涯学のような場所で、こうしてさまざまな分野の方と議論できることはとてもありがたいです。
寺本:私自身も、実験心理学とは性質の異なるアプローチで研究なさっている松本先生のお考えが伺えて、非常に刺激を受けました。調査の進捗を、そしてその後の議論を楽しみにしています。
<プロフィール>
松本卓也(まつもと・たくや)信州大学理学部・助教
奈良県出身。京都大学大学院理学研究科生物科学専攻動物学系(人類進化論研究室)で、京都府嵐山に生息するニホンザルや、タンザニアのマハレ山塊国立公園に生息する野生チンパンジーのフィールドワークを行い、2019年に博士号(理学)取得。2021年より現職。チンパンジー調査を続けながら長野県の地獄谷野猿公苑などのニホンザルの調査も行っている。
生涯学公募研究
野生チンパンジー社会における高齢個体の生き様:人口動態と行動観察による再定位

寺本渉(てらもと・わたる)熊本大学大学院人文社会科学研究部・教授
秋田県生まれ。専門は知覚心理学・認知心理学。脳波計やfMRI、VR装置など多様な装置を用いて、人間の知覚の身体性や多感覚統合を明らかにする研究に従事している。2004年神戸大学大学院文化学研究科で博士号(学術)取得後、産業総合研究所やドイツのマックス・プランク研究所、東北大学電気通信研究所での研究を経て、室蘭工業大学大学院工学研究科准教授に。2015年熊本大学文学部に着任し、2018年より現職。生涯学プロジェクトでは、知覚・認知心理班(知覚系の知識獲得機構の加齢変化)の代表を務める。
インタビューはこちら

取材日 2024.3.16
取材・構成:江口絵理
撮影:金子守恵