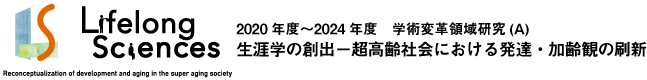<記事公開日> 2023.6.6
現代女性の健康と人生を支える「女性のための生涯学」
江川美保(京都大学医学研究科) × 筒井淳也(立命館大学産業社会学部)
少子化問題を扱う社会学にとっても重要な分野
筒井:生涯学に「女性」を対象とする研究が加わってくださったことの意義は非常に大きいと思っています。私の専門は家族社会学で、少子化問題について政治家の方やメディアから聞かれることが多いこともあり、江川さんのご研究を興味深く拝見してきました。
江川:ありがとうございます。女性は子どもを産み育てる性として、生涯にわたって女性ホルモンの影響を強く受けます。女性が心地よく生きていくにも社会参加するにも、その影響を理解し、対応するための指針となる「女性のための生涯学」が必要だと考えています。
筒井:江川さんは婦人科医として患者さんを診察されて30年とのことですが、なぜ婦人科を専門とされたのでしょうか。
江川:もともと精神医学や心身医学に関心がありましたが、母性を守りたいという気持ちと、更年期障害というテーマなら心と体の両方を診られるという考えから、女性に寄り添う婦人科に進みました。
ところが現職に着任してからは、思いのほか重症の月経前症候群(PMS)で苦しんでいる患者さんに出会うことが多かったのです。そこで特にPMSについて深く考えるようになりました。

PMSの症状は、頭痛やむくみ、抑うつなど非常に幅広く、程度も多様です。そのうえ、本人はとても辛いのに検査をしてもなんの異常も出てこない。とくに私がいま勤務しているような大学病院には、一般的な治療では軽快しなかったという患者さんが来られます。「次の手」を探るために、まず私は患者さんの困りごとを積極的に訊ねることから始めました。
すると、一部の患者さんは自分の症状のメモを基に、限られた時間で一生懸命語ってくれるようになったんです。日常生活の中でどのようなときに辛くなり、どのようなことを習慣にすると調子がよくなるか。どの薬を使ったときには軽快し、どの薬では変化がなかったか。
対話を重視したそのような診療の中で、医師の私が提案する治療薬やセルフケアの選択肢のなかから自分の意思で選びとれる方も出てきました。
そうした患者さんは「自分を観察し、記録し、医師と話し合い、自分を少し変える」ことを繰り返すことによって、ご本人の自己効力感が高まり、症状改善にもつながっているように見えました。
それを確かめるべく、生涯学の公募研究では、以前に開発した症状記録のスマホアプリを用いて、「セルフモニタリングとセルフケアのアドバイスを受けることがどれぐらい症状改善に寄与するか」を検証しています。
加えて、PMSの客観的な指標を得たいと考えています。PMSの特徴は医療機関での一般的な検査ではとらえられないので、脳活動に着目しました。fMRIを使って月経前と月経後の脳機能の違いを調べています。
平均的な「ヒト」と、異質性をもつ個々の人間
筒井:社会学には、人の「異質性」に注目するという特徴があります。たとえば、調査の際に「二〇代男性」に共通の傾向を見ようとしても、人によって所得も生活スタイルも違いますよね。
きっとPMSの患者さんにも、放っておいても記録をつけるような人と、つけてくださいと言われて初めてつけ始める人がいるだろうと思います。そういう状況から「何のおかげで症状改善したのか」という因果関係を突き止めるのはなかなか大変だろうと推察しています。
江川:はい、その通りだと思いますが、今回は医学研究の本流に沿ってランダム化比較試験を行いました。人をできるだけ平均的で偏りのない存在として「この介入法はこの症状に効くか否か」を調べるスタイルです。
しかし、私がふだん見ている臨床の現場は異質性だらけです。ほかに疾患をもっている人もいますし、トラウマのある人、仕事・育児・介護でストレスを抱えている人、あるいは発達障害の子の療育に多くのエネルギーをとられている母親がPMSに悩んでいることも多いです。
マルチタスクの生活では、自分のケアが二の次になってしまうのも無理はありません。とりわけ次世代を生み、社会の再生産を担う20-40代において、そのような時期は多かれ少なかれあるものでしょう。
ゆえに、臨床の現場で一律に理想の形を押しつけることには意味がありません。起き上がることもできない人に「運動が大事です」と言ったって、ふさぎこんでいる人に「規則正しく、栄養バランスのとれた食事を毎食作りましょう」と言ったって、解決にはなりませんから……。個々に、「今できるセルフケアは何だろうか」と患者さんとともに考えることから始めます。
「標準的なライフコース」があるという思い込み

筒井:私が代表を務める高年社会参加班では、「生涯観は時代とともにひとりでに変化している」ということを前提として研究を進めています。たとえば団塊の世代の生涯観とその親の世代では平均寿命も一家族あたりの子どもの数も異なり、価値観もライフコースも違ったものになります。
しかし人は「標準的なライフコース」というものがあると思い込み、それは自分の子や孫の世代でも変わらないと考えてしまう。そこからいろんなきしみが生まれます。江川さんの領域でいうと、女性の生涯の月経回数が昔と今ではまったく異なる、という点が象徴的だと思いますが。
江川:その通りです。昔の女性が一生涯に経験した月経は50回ですが、少産化・晩産化の進んだ現代では450回。実に10倍近くに及びます。
子宮内膜が厚くなっては剥がれ落ちる月経を数多く繰り返し、かつ妊娠を経験しないライフスタイルでは、子宮内膜症を発症するリスクが高まることが知られています。子宮内膜症は不妊症の原因にもなります。いまの婦人科の知見では、月経痛や過多月経やPMSには低用量ピルを用いた月経コントロールが推奨されています。
過去の女性が蓄積してきた「おばあちゃんの知恵袋」には、そうした教えは入っていません。現代の女性が健やかに生き、子どもを産むためには、現代的な「月経とつきあう知恵」が必要なんですよね。
ケアを担う女性を無視した「女性活躍」という言葉
江川:社会学の筒井さんに伺ってみたかったのですが、近年よく「女性活躍」と言われますよね。その「女性活躍」とは、組織のリーダーになったり、数字に反映される成果を出したり、つまり家庭の外での活動を指しているように感じます。

しかし、そうした仕事ではなくとも、家の中で大きな働きをしている女性がたくさんいます。家族の中の弱いメンバーに寄り添い、家庭の大きなトラブルを回避し、生活の安寧を保つことに大きく貢献してきた人たちです。
女性は家庭内にとどまるべきだと言いたいわけではなく、性別にかかわらず、そういう役割を果たす人の存在が必要な時期は、たいていの家族にあります。その人たちに「もっと“外で”活躍を」と言うことに違和感を覚えるのですが。
筒井:おっしゃる通り、家族内の育児や介護、看病などのさまざまな場面で女性が働いてきたからこそ家族の生活が機能し、社会が成り立っているのですから、「家庭にいる女性は活躍していない」という考え方はおかしいと私も思います。実際、社会学者は「女性活躍」という言葉をほとんど使いません。
社会学ではこの30~40年にわたって、従来、女性の役割とされてきた仕事、つまり「ケア」の仕事について、インテンシブに議論がなされてきました。
どのような議論が行われているかについてはまた別の機会にでもお話しできればと思いますが、私が望むのは、「ケアの経験をもつ女性に、社会の意志決定の場にいてほしい」ということです。
いま政策を決めている人たちは主に中高年男性たちで、ケアの経験をほとんど持たず、ケアに関して政策として何が必要か、想像がついていません。

たとえば、三世帯同居の家庭を標準的な、あるいは理想的なモデルと考え、画一的な支援策を作ってしまう。私は政府の審議会などに呼ばれると、一律の制度でなく柔軟性の高い制度を、と訴えるのですがなかなか聞いてもらえないのが現実なのです。
社会学者には、“社会と長くつきあうお医者さん”のような側面があり、メディアや政治家の方からしばしば、「先生、児童手当をいくら上げれば日本の出生力が上がりますか」という質問を投げかけられます。しかし、少子化について「これを飲めばきれいさっぱり完治する」というような特効薬はないんです。江川さんが診ていらっしゃるPMSと通じるものがあるように思いました。
江川:ちょっと極端な言い方になりますが、私はあるとき、PMSに関して“治す医者”をやめたんです。これだけですべてが解決する、という魔法の薬はない。
薬を使わないという意味ではありません。ピルも漢方薬も積極的に使います。しかしそれは症状を押さえ込むためではなく、体の調子を全体的に整えていくため。
ピルで体調の波がおだやかになっている間に、私は患者さんの「好循環のスイッチ」を入れようとしています。好循環とは、自分の体を理解し、調子を整えるためにできることを判断し、主体的に取り組むようになることです。運動でも、栄養改善でも、マインドセットの変革でもいい。
自分の在り方を良い悪いとジャッジすることが目的ではない。自分にとって必要なことやできることに一つずつ取り組むこと、そうした試行錯誤をコツコツとやっていくことが「生きる」ということなんじゃないかと思うんです。私はそれを側面から支援する立場だと思っています、“治す”のではなくて。
患者さんを育てる、というと僭越ですが、医師として医学的な根拠に基づいて選択肢を提示し、患者さん自身の変化を応援する、と言ったらいいでしょうか。
筒井:非常に示唆に富むお話です。政治家の方やメディアの方に「少子化問題に単一の解決策はない」と言ってもわかってもらいにくく、ずっと歯がゆい思いをしてきたのですが、それに対してヒントをもらったように思います。
更年期は、生涯における「衰退の始まり」ではない

筒井:江川さんは生涯学後期の公募研究にも採択されていますね。後期は更年期障害を対象とした研究とのことですが。
江川:はい、前期公募研究でテーマとしたPMSと密接につながっています。更年期障害で来院される患者さんは「40代後半の今でこんなに心身が弱ってしまうなら、50代以降はもっと辛くなる一方に違いない」とおっしゃいます。
しかし私はあるとき、更年期に差し掛かる前からPMSで来院されていた患者さんで、好循環の歯車を回し始めた方の多くは、更年期を元気に過ごされる傾向があることに気づきました。
たしかに、ホットフラッシュなど、女性ホルモンの減少によって出てくる症状はあります(それらにはホルモン補充療法が良く効きます)。ただ、疲労感やメンタル不調といったそのほかの症状は、PMSで苦しんでいた間にご自身で取り組まれたセルフケア、たとえば鉄やたんぱく質などの欠乏しがちな栄養を積極的に摂る生活改善などによって、防がれているように思われるのです。
つまり、女性は月経があるうちから適切なセルフケアをしておくことが健やかな更年期に繋がるのではではないか。そう考えて後期の研究を着想しました。
また、更年期症状もPMSと同様に、セルフモニタリングによって症状改善があるかもしれません。そうしたことも研究のうちに入っています。
婦人科医としてあらゆるライフステージの女性を診察してきた経験から、私は、更年期は必ずしも「衰退の始まり」ではないと考えるようになりました。更年期は、月経がある間(社会の再生産を担う時期)に課せられた役割から解放され、自分らしさを再び見いだしていく(人生を統合する)期間だと思います。
そんな風に患者さんにお話しすると、患者さんは「じゃあ、卒業を楽しみにがんばりますわ」とおっしゃる。そして数年が経っていよいよ閉経となり、「これで卒業ですよ、おめでとう」とお知らせしたときの晴れ晴れとした顔。そして、だんだんと自分を大事にするライフスタイルを選んでいくようになる患者さんの成長を見るのが、婦人科医としての醍醐味です。
ただ、こうしたこと伝えられるのは私が外来で接する女性たちだけで、数が限られてしまいます。ですから生涯学の場で研究を進め、その成果を広めたいと思っています。
筒井:期待しています。お話にたいへん刺激を受けました。ありがとうございました。
<プロフィール>
江川美保(えがわ・みほ)京都大学医学研究科婦人科学産科学・助教
広島県出身。2014年より現職。京都大学医学部附属病院で月経前症候群や更年期障害などの診察にあたりつつ、疾患の治療だけでなく女性の健康の底上げをテーマとして、精神医学・脳科学・公衆衛生学・保健学・情報学など各領域の専門家や企業と連携して研究を行っている。
生涯学前期公募研究:性周期を軸にした「女性の生涯学」の提案と社会参加への応用
生涯学後期公募研究:更年期の鉄欠乏とメンタル不調の関連:女性ホルモンの衰退に抗わない予防医学の開拓

筒井淳也(つつい・じゅんや) 立命館大学産業社会学部・教授
福岡県出身。2014年から現職。計量社会学・家族社会学を専門とし、社会調査によるデータをもとに日本の未婚化や成人親子関係など家族のあり方や変化を描き出すかたわら、行政への提言や一般向け書籍の執筆にも力を注いでいる。著書に『仕事と家族』(中公新書)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書)、『社会を知るためには』(ちくまプリマー新書)、『社会学:非サイエンス的な知の居場所』(岩波書店)ほか多数。

取材日 2023.3.20
取材・構成:江口絵理
撮影:楠本涼