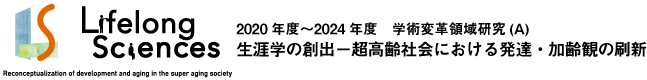笠井賢紀さんは、高齢者へのインタビュー調査を軸として、伝統的な集落や半世紀前に作られたニュータウンの地域社会を研究されています。知覚・認知心理班で高齢者の知覚を調べている日高聡太さんが笠井さんに、生涯学で目指すものを尋ねました。
<記事公開日> 2024.1.29
地域社会を機能させる「高齢者の力」に迫る
笠井賢紀(慶應義塾大学法学部) × 日高聡太(上智大学総合人間科学部)
記述されていない、高齢者の“可能性”
日高:笠井さんはこれまで、日本各地の伝統的な集落で長く続いてきた風習である「左義長(さぎちょう)」や、「伊勢講(いせこう)」の調査をされてきたとのこと。そうした行事において高齢者の果たす役割が大きいことから、生涯学プロジェクトへの参加をお考えになったのでしょうか?
笠井:生涯学のコンセプトには、老いることを解消すべき「課題」としてではなく、ポジティブにとらえなおそうという意気込みが謳われていますよね。生涯学の公募研究に応募したのは、そこに非常に共感したことが大きな理由の一つでした。私が、地域社会と高齢者の調査をしていてしばしば実感するのは、「高齢者本人や社会が気づいていないだけで、高齢者は多くの可能性をもっている」ということなんです。
日高:正月飾りを持ち寄って燃やす左義長や、お伊勢参りに関する宴を催す伊勢講は、いずれも神事に関係がありますね。宗教的な行事で高齢者に大きな役割が与えられていることで高齢者が生き生きして、地域社会がうまく回っていくのでしょうか。
笠井:実は、とりわけ高齢者に重要な役割が与えられているわけではないんです。左義長においては飾りを結わえるための蔓や燃やすための藁を調達するのは子どもたちの役目と決まっていますし、伊勢講で新年会を催す幹事役は輪番制が基本です。特定の誰かに権力が集中し、役割が固定化することのないこうした工夫が、これらの風習を長く続かせてきたのでしょう。
いま70代後半以降の高齢者にはこうした知恵が蓄積されています。現代社会ではあまり顧みられることがなく、ご本人たちも「仕事を引退して年老いた自分なんて役に立たない」と卑下されることがありますが、私は「いや、蓄積されてきた知恵は社会に必要なものではないか」と考えていまして、それを記述しようとしています。
日高:何百年と続いてきた左義長や伊勢講も、近年では生活スタイルの変化によって消滅する地域が多いと聞きます。それでも、高齢者が左義長や伊勢講で身につけてきた知恵は役に立つ、と。
笠井:はい。伝統的な風習を研究していると、「貴重な文化を守ろう」とか「古き良き時代に帰るべきだ」と考えているのだろうと思われがちですが、私は社会学者として、左義長や伊勢講などの民俗が社会をうまく回すために果たしてきた機能を明らかにしたいと考えて研究をしています。本質がわかれば、伝統的集落以外の場所にもそれを転用する可能性が拓けるのではないかと思っているんです。
日高:左義長や伊勢講はどのような機能を果たしてきたとお考えですか?
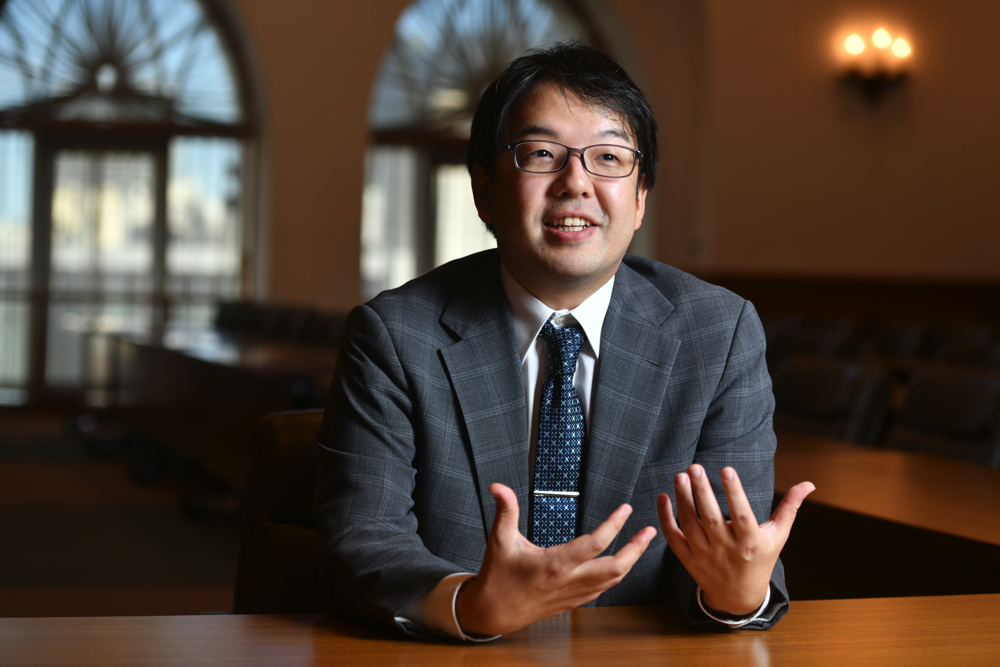
笠井:多様性を受容しようという文脈で、理想像として「共生社会」という言葉がよく使われますが、私は、共生社会とは“目指すべきもの”ではなく、多様な、ときには決して相容れないような価値観をもつ人間同士が否応なく一つの社会でともに生きていかねばならない“現状”のことだと思っているんです。
左義長や伊勢講は、価値観の違いにあまり左右されない「原初的な楽しみ」を必ず含んでいます。炎を囲む楽しみ、集まって酒を酌み交わす楽しみ……。そうした行事や準備作業に、時には嫌々ながらも全員が参加し、顔を合わせて一緒に何かをすることを通じて個人間の軋轢がぼかされ、地域社会がうまく回っていく。
つまり、左義長や伊勢講などは、「共生社会をうまく回すためのレパートリー」ではないか。
日高:「レパートリー」とは、ユニークな表現ですね。バリエーションがあり、かつ、多くの人に予測ができるもの、ということでしょうか。
笠井:はい、料理のレパートリー、カラオケのレパートリーなどのように、いくつかの選択肢があり、当人だけでなくほかの人も「そうか、あれのことだな」と予測ができる。いまの高齢者は、共生社会のレパートリーを多く身につけています。
日高:地域社会が健全に続いていくには、血縁内だけでない他世代との交流が必要だと言われますが、子どもに役割が与えられている行事ならそれも実現されますね。
笠井:そうなんです、原初的な楽しみが含まれていること、神様やご先祖様、暦などにことよせた「物語」があること、子どもが参加すること、輪番制にすること、など、レパートリーとして残ってきたものには、さまざまな工夫が息づいています。海外でいえば、子どもたちが地域を練り歩き、お菓子をもらうハロウィンもそうしたレパートリーの一つと言えるかもしれません。
インタビューで「手続き記憶」を掘り起こす
日高:この生涯学プロジェクトでは、笠井さんは1970年代につくられたニュータウンも調査の対象とされていますね。ニュータウンには地域に根付いた行事、すなわち共生社会のレパートリーがないわけですが……。
笠井:はい、その代わりに自治組織がどのように運営されてきたかを調査しています。私の調査しているニュータウンでは、いまの高齢者が自治会の運営に重要な役割を果たしてきました。彼らが現役のときは企業社会でも組合運動が盛んで、そこで身につけたノウハウが、ニュータウンの自治組織にも見事に応用されていたことがわかりました。
とはいえ、70代後半以降の方々にお話を聞かせてくださいと頼みにいくと、「現役時代は技師だったから、その時の経験は自治会活動の役には立っていない」などと言われるんです。でも人生史を一通り聞いてみると、人の話をきちんとメモをとって聞くとか、弱い立場に置かれた人への配慮がある、とか、その人が人生で得てきたものが自治活動に生きていることは明らかなんです。ご本人が意識していないだけで。
日高:心理学では、人間の記憶には自分できちんと意味や内容を説明できる「宣言的記憶」と、包丁の使い方や自転車の乗り方のように、身体に染みついているが自分で説明するのは難しい「手続き記憶」がある、としています。インタビューされた方は宣言的記憶をもとに話しているのだけれど、笠井さんは手続き記憶を掘り起こされているのかもしれませんね。
笠井:なるほど、そのように分けて考えてみたことはありませんでした。頭が整理されます。
視覚の衰えはネタにできるが、聴覚は?
笠井:高齢者の加齢と知覚の関係を心理学的に研究されている日高先生に、純粋な興味から、ちょっと伺ってみたいことがあるのです。人が自身の老いを「ネタ」として笑いにできるのはどれぐらい衰えたときなのでしょうか? たとえば40代だと「老眼ネタ」はかなり一般的ですよね。でもほかの知覚ではあまりないような。
日高:「サクセスフル・エイジング」という語をご存じでしょうか。生涯学に参加されている、心理学の権藤恭之さん(大阪大学)のお話によると、サクセスフル・エイジングとは、年を重ねても衰えないことではなく、「さまざまな方法で衰えをカバーしつつ、老いを受容して年を重ねていくこと」を指すのだそうです。

ここからは私の研究ともからむのですが、高齢になると視覚や聴覚などの知覚が落ちていきます。ただ、単に落ちるばかりではありません。会話の際に聴覚だけでなく視覚も手がかりにして全体を理解する、というように、ある知覚の衰えを別の知覚で補う傾向が実験を通じてわかってきています。
サクセスフル・エイジングの考え方とその知見を合わせると、加齢によってできないことが出てきたときに、すべての知覚を若いときのまま保とうと考えるのではなく、聴覚が落ちたけれど視覚で補えば会話は理解できる、とか、記憶力は落ちたけど手帳をつけて物忘れを防ごう、といった“自覚”と“補償”によって不便に対処しながら、老いを内面で受容していく、というプロセスが望ましいのだろうと推測しています。
ネタにして笑えるようになるには、衰えたという自覚を経て、受容が進んだ状態になることが必要なのではないかと思います。
笠井:日高さんは知覚の衰えの“自覚”に関する調査もやっていらっしゃいましたね。
日高:高齢者の日常生活における、感覚の「困りごと」を40代から70代の男女878人に尋ねてみました。すると、視覚に関してはかなりの割合で困っている人がいて、ただし眼鏡やコンタクトの補助具によってそれを解決している。
その一方で聴覚に関しては、70代で困っていると答える人の割合が増えるには増えるものの、客観的なデータからすると聴覚がだいぶ落ちている人の数はずっと多いはずなんです。つまり、自覚されていない。
ということは、受容よりも前の段階なので、聴覚をネタにする(できている)人の数は70代でもまだ少ないでしょう。自覚がないと、会話がうまくいかなくなる。すると外界から入る情報が減ることで結果的に認知機能に悪影響が出る恐れもあるので、聴覚の衰えについてはより自覚してもらえるよう発信したいところです。
笠井:「衰えないように〇〇をしましょう」と提示するための研究は数多く存在し、そうした研究はもちろん大事ですが、健康寿命は無限に伸ばせるわけではなく、必ず終わりがありますよね。日高先生のお話で、衰えを自覚・受容し、うまくつきあって生きていく方法を提示する研究の重要性に気づかされました。
加齢とともに上がる知性
笠井:知覚と異なり、社会学的には加齢につれて上がっていくものもあります。たとえば、先ほどお話しした「共生社会のレパートリー」は増えていきますし、個人的にもさまざまな場面に遭遇することで経験値が上がっていきますよね。それこそ、老いや死の受容に関してはさまざまな場面に立ち会うことで向き合い方が成熟していくものだろうと思います。
日高:生涯学は今年度でちょうど全5年間の中間地点を折り返すところで、これまでの研究で見えてきたことを整理しているのですが、領域代表の月浦崇さんがキーワードとして挙げられたのは、加齢を「衰え」ではなく「成熟」としてとらえよう、ということでした。
笠井:年を重ねることのポジティブな面に目が向く言葉ですね。
日高:高齢者の知能を測るテストでは、言語や情報の処理能力、瞬発的な記憶力などを測るのですが、それらはもっぱら「頭の回転の速さ」の指標である流動性知能と呼ばれるものです。ただ、人生の経験値など、長期的に蓄積されていく知性は結晶性知性と呼ばれ、加齢による衰えの影響は少ないと言われています。知能テストでは測れていないものが広く存在することをいまあらためて実感しています。
いまの高齢世代のためだけでなく、未来の高齢世代のためにも
笠井:一つ、忘れてはいけないこととして、高齢になったら自動的に経験値が上がるわけではないんですよね。私たち現役世代は、いまの70代後半以上の高齢者が蓄積してきたような共生社会のレパートリーを学ぶ機会がさほどないまま年を重ねつつあります。私たちが社会に出たときには組合運動などもすでに下火になっていましたし、地域社会に関わりを持たずに暮らしてきた人も多い。地域の共生社会をうまく回す経験値は総じて低い状態と言えます。
私たちの世代が高齢になったとき、街づくりや超高層マンションのコミュニティなどの新たな文脈で、既存の様々なレパートリーに含まれていた工夫を転用するとうまくいくこともあるでしょう。
いま、この研究をやっておくことの意義は、いまの高齢者の可能性を明らかにするだけでなく、将来の高齢世代がいまの高齢世代と同じぐらいに、あるいはもっと大きな可能性を見いだせるぐらいに成熟するためには何が必要かを明らかにすることにもあるのではないか。
古きよきものを守ろう、高齢者を尊敬しよう、ではなく、いまの現役世代、子ども世代にとってのよりよき未来のための研究でもあると思います。実はこれまでにそのように考えたことはなかったのですが、今日、日高さんとお話ししていて気づかされました。ありがとうございます。
日高:私こそ、高齢者の可能性や心理学の手法で測れていないものについて多くの発見がありました。いい機会をありがとうございました。
※左義長や伊勢講は地域によって違いがあります。本記事では笠井賢紀さんの研究対象地域(滋賀県栗東市)の事例に基づいて対談を行いました。
※日高聡太さんの「高」は、正しくは「はしごだか」です。
<プロフィール>
笠井賢紀(かさい・よしのり)慶應義塾大学法学部・准教授
北海道出身。横須賀市役所、龍谷大学などを経て2022年より現職。生活史の聞き取りを軸として、住民自治組織や民俗など、地域社会のありようを調査・研究してきた。著書に『栗東市の左義長からみる地域社会』(サンライズ出版)、共編著に『共生の思想と作法-共によりよく生き続けるために-』(法律文化社)など。
生涯学後期公募研究:高齢者の地域社会貢献活動についての社会学的研究:地域史と人生史の分析を通じて

日高聡太(ひだか・そうた) 上智大学総合人間科学部・教授
取材日 2023.11.20
取材・構成:江口絵理
撮影:門間新弥